※この記事はネタバレを含みます。未見の方はご注意ください。
劇場で観たので、もう3年近く経っているのだけど、当時のメモを元に書き起こしてみる。
日本ではあまり盛り上がらず、どんどん上映館も減っていったのを記憶している。第2次世界大戦のダンケルクの撤退作戦なんてあまり有名ではないし、敵を打ち破った戦いでもないし、盛り上がりようがなかったのかもしれない。
自分にとっては、「インターステラー」の後のクリストファー・ノーラン作品だったので、期待も大きかった。「メメント」で変なことを考える人が出てきたと思ったのがいつだったか、まだシネクイントがパルコの最上階にあった頃、単館上映だったと思う。
マイナーなカルトシネマの監督が、今では、ハリウッドで超大作を撮るようになり、次作を期待してしまうまでになった。同じ時代を生きている面白さを感じさせてくれる。
「ダンケルク」は、フランス北岸のダンケルクから、40万もの兵を対岸のイギリスへ撤退させる作戦を描いた100分ぐらいの短い映画だ。100分の中で、3つの視点で、物語が並行して進んでいく。ただ3つの視点があるのではなく、1週間、1日、1時間と時間の経過が異なるのが特徴だ。
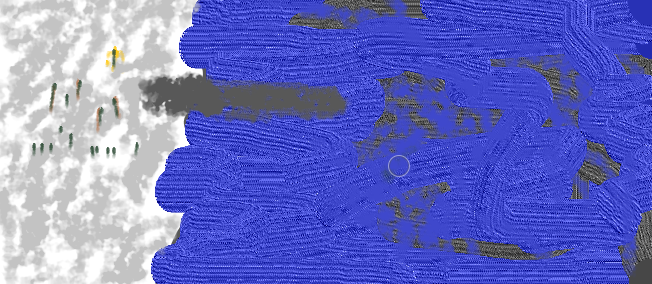
1つめは、ダンケルク沿岸で船を待つ兵士たちの永遠とも思える1週間だ。追い詰められ、逃げることもできず、ただ救援を待つことしかできない。兵士たちは恐慌し、狼狽し、状況の変化にただ翻弄されてゆく。重力に縛り付けられた彼らの時間の歩みは遅々として進まない。誰からも見捨てられたかのように海辺でたたずむ彼らには、救援の船も援護の戦闘機も見えやしない。近づいていることにすら気づきようもない。
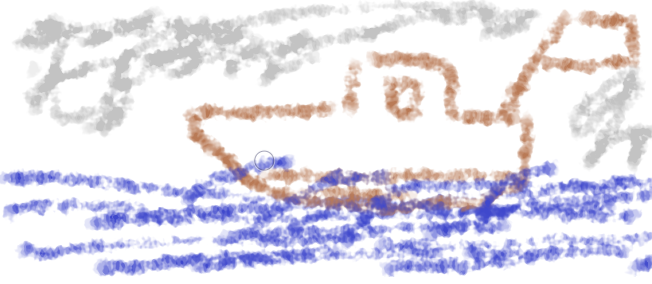
2つめは、兵士を救うために、自らの船でダンケルクを目指す民間人の1日だ。ボランティアで、ただただ兵士たちを救うという使命感だけで、彼らは危険な戦場に船を出す。身を守るものも武器も持たずに、船は、少しずつ地理的な距離と時間的な距離を縮めてゆく。
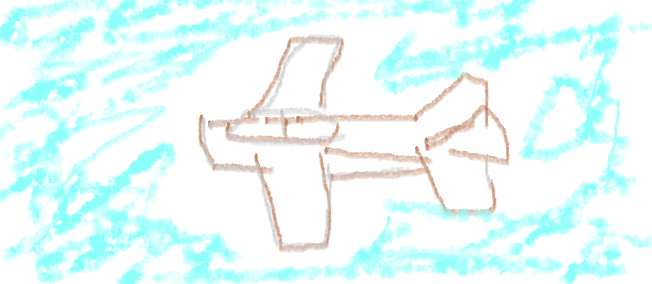
3つめは、上空から援護する戦闘機乗りたちのわずか1時間の経過だ。兵と船が死闘する地平と水平の交わる平面を俯瞰する様は、神の目線のようにすら思える。波にのまれ死の恐怖にさらされる撤退部隊に比べれば、空はあまりにも安全で、圧倒的な火力は、天のいかづちのようだ。
まったく異なる視点が交わる瞬間が不意に訪れたとき、観客は、そのど真ん中で戦慄する。アナログな第二次世界大戦だけれど、とてもSF的なストーリーテリングなのだ。
ダンケルクの援護に向かう戦闘機スピットファイアの乗組員たちの1時間と浜辺の兵士の1週間が、作品の時間軸では同等に経過する。動くスピードが速いほど、相対的に時間の経過が遅くなる相対性理論を思わせるような時間の流れだ。日付と時間だけを記して場面が切り替わるだけなので、正直、映画が始まってから理解するまでに、少し時間を要した。
複数の視点が交わった瞬間に、ハッとさせられ、物語の全貌が明らかになってゆく驚きは、期待通りで楽しい。クリストファー・ノーランらしいなとほくそ笑んでしまう。
楽しい物語ではない。銃弾や爆撃、水没からの絶え間ないプレッシャーで胃がキリリとするシーンが続く。どのシーンも心理的圧迫感が強く、スピットファイアのエンジン音は無機質で爆音で、ちょっと疲れてしまってスピーカーのボリュームを下げて欲しくなったくらいだ。
けれども、何度か危機を脱するシーンを観ると、これは「生き残る物語」なのだと気づく。すると、少なくとも、この登場人物は生き残るだろうと当たりをつけてしまう。少し安心して、緊迫感はやや薄れた。今思うと戦場の人たちは、自分は大丈夫と錯覚することで、なんとか目の前の出来事に対処できたのではないか。でなければ発狂してしまう。観客のぼくらは、そうやって登場人物たちに、同化させられていたのかもしれない。
異なる視点で並行に描くことで、物語が立体的になり、観客に対し状況が徐徐につまびらかになってゆく。浜辺の兵士たち、助けに行く民間人、援護する戦闘機乗り。より強く心に残ったのは、時間軸が交わったあとのそれぞれの姿だった。
戦闘機を敵の手に渡さないため、敵前に不時着した飛行機乗りの思いに涙が流れた。帰還できる燃料がないとわかってもなお、援護に向かった彼はどこまで計算していたのだろう。無事、援護を果たしたのち、戦闘機を捨てずに、着陸を試みるシーンは、なぜか涙をさそう。なにかを必死に成し遂げたあとに、さらに上を目指す、欲深さ、完璧を目指す志し、ここまでやったんだからいいだろうという甘さの無さに涙がでたのだと思う。
民間人の船の上で、恐慌状態に陥った負傷兵が男の子を突き飛ばして殺してしまう。しかし、同乗していた友人とその祖父は、そのことを伏せたまま、兵士を見送る。あの物言わぬシーンが、心に残る。誰も悪くないのに、酷いことが起こってしまった悲しみを真正面から受け止めるまなざしがあった。だからこそ、死んでしまった男の子の生前の思いを叶えた新聞記事が意味深いものとなる。
最後に、逃げ帰ったことで非難されるのを恐れる兵士の姿だ。敵に敗れ、なにもできずに戻ってきた自分を、みんなが役立たずと罵るに違いないと顔をあげることができない。おそらく、彼自身が、自分をそう見ていたのだろう。何も恥じることはない。よく生きて帰ってきた。と言ってくれる街の人々の言葉に涙する彼のとまどいにつられ、涙してしまうのはどうしてだろう。ベトナム帰還兵に対する風当たりとは真逆な出迎えに、まだ未来があることを感じずにはいられなかった。チャーチル首相の有名な演説が響く。
ドイツという共通の敵がいるという特異な状況下だけれども、ひとりひとりが自分の役割を、結果はともかく精一杯果たそうとして、どんな失敗も誰のせいにもせず、許すことができる空気が流れていた。自分には厳しく、他者には寛容に接することで、困難を乗り越えようとするこの空気こそ、今の世の中に必要だから、「ダンケルク」は作られたのではなかろうか。そう思わずにはいられなかった。
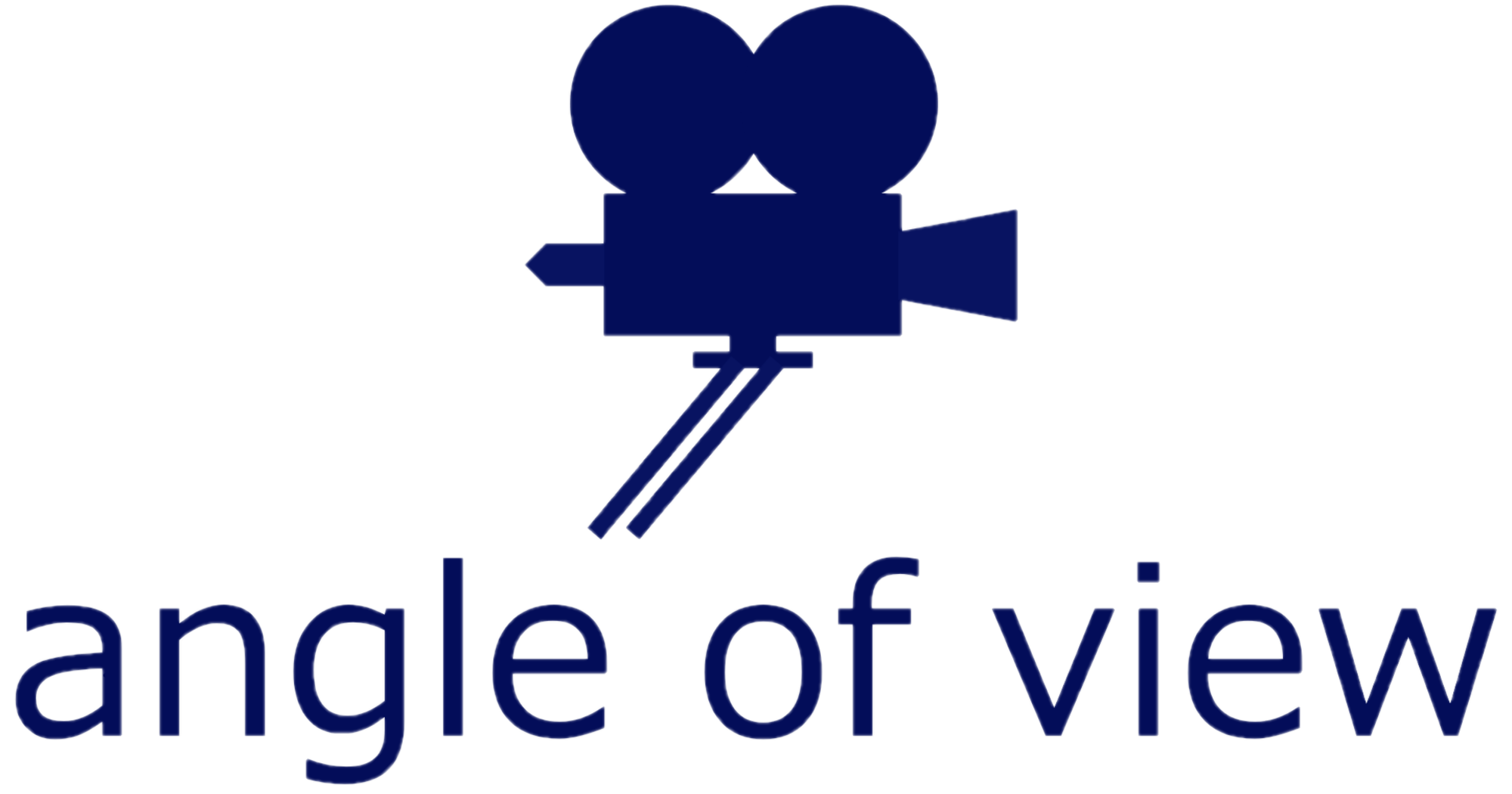








コメント