初めて、自分でチケットを買って演劇を見たのは下北沢の本多劇場でした。寺山修司作の独り芝居で妙に心打たれて、しばらく演劇を良く見に行くようになったのを思い出します。下北沢は、小劇場の街で、知っている人にすれば懐かしく、知らない人でもサブカルのイメージのあるごみごみした街なのではないでしょうか。下北沢で、演劇に没頭する青年と、彼を支える健気な女の子の物語は、まるで遠い昔からある昭和臭ささえ感じる何度となく描かれたテーマです。手垢がつきすぎていて、よくチャレンジしたなと思わずにはいられません。
下北沢と言えば、小田急線と井の頭線が交差し、街は踏切で分断され、ひっきりなしに行き交う電車の走行音が印象的です。若く孤独な日々は、どこか遠くへ行くこともできず、とぼとぼと線路脇の道を歩きながら、夕闇に浮かび上がる電車内の明かりがただただ眩しかったのを思い出します。この映画は、遠い日の記憶がまるで昨日のように感じさせるところがあります。下北沢から踏み切りがなくなったとしても、小田急線が地下に潜ってしまったとしても在りし日の姿のザラザラした苦みは残りつづけているのです。
ギリシャ悲劇が、なぜ悲劇なのか。ぼくの解釈はこうです。ギリシャ悲劇は、どの場面、どのシーンでも、登場人物は考え得る限り最善の言葉を発し、最善の行いをします。常に。いかなる場合も。それなのに、待つのは苦しく悲しい結末なのです。回避不能なその道程を悲劇と呼ぶのだと考えています。
対して喜劇とは何か。ぼくの解釈はこうです。偶然と人の愚かさが織りなす様々な事象がパズルのように組み合わさった1枚の絵画です。ほとんどの出来事が偶然で、ほとんどの人の行為は愚かです。描きあがった絵画には想像もしなかったおかしみがあるものです。悲しくても、楽しくても、虚しくても、悲劇でないものは、すべて喜劇だと考えています。
この解釈でいうと、ぼくには、この物語は喜劇と思われます。主人公の永くんは、プライドが高く、狭量な心の持ち主なのが災いして、人を傷つけてばかりで、まわりも自分も追い詰めていくのですから、まったく必然性があるように思われません。自分で自分を苦しめている様は、端から見ていると、実に面白いものですが、そのおかしみをどうもうまく表現できていないようなのです。喜劇としての出来はあまり感心できるものではなさそうです。
演劇を作る。というクリエイティブな人間にとって、プライドの高さや他人の優秀さを認めない狭量さや生活や将来のことを顧みない無計画さが必要なのだと、凡庸なぼくは考えました。素晴らしい傑作と引き換えに、大切なものを失う物語もあります。
そのひとつ、「ラ・ラ・ランド」という傑作ミュージカル映画が、音楽家と役者という2人のクリエイティブな人間のぶつかり合いと切ない別れを描き、話題となりました。犠牲と成果と対比し、あり得たかもしれない未来をミュージカル調に描ききることで、切ない時の流れを表現しました。
けれども、「劇場」の彼は、何も成果をあげません。犠牲だけで成果がないのです。なんとストイックな男でしょう。クリエイティブなものが作れないクリエイティブな人間はどこに行けば良いのでしょう。何をすれば良いのでしょう。もちろん商業的な成功と才能は必ずしも結びつくものではありません。いつか彼を発見してくれる時代があるかもしれません。ならば、続けることこそが大切なのかもしれません。
彼の将来を心配する人なら言うかもしれません。まずは、生活基盤をしっかり持つことを考えてもいいんじゃないかと。確かに、会社勤めをしながら、創作活動を続け、対価が得られるようになり、フリーになった作家や音楽家はたくさんいます。でも、彼には、すべてをなげうって打ち込む姿こそが大切なのです。どうしようもなくなるまで。一歩も先に進めなくなるまで。まだ、続けられる。もう少し続けられる。
続けたとして、どこにも行けはしません。でも慰めはあります。プライドの高さが壁になり、自分でできなくても、この作品が慰めてくれます。諦めの悪さを慰め、わずかに自尊心をくすぐり、あり得たかもしれない未来を描き、かげろうのような肯定感を醸し出してくれます。
惨めな姿で街を徘徊しても、山崎賢人の美しい顔が慰めになります。何も変わっていないのに、夢を語るとなんだか誇らしくなります。懐かしい日々は、その頃、ちっともそう思っていなかったのに、楽しかったような、充実していたかのような錯覚を呼び起こします。心を洗い流してくれます。これをカタルシスといいます。本来の意味とは違うかもしれませんが、最近はカタルシスと言います。
この映画で素敵だったのは、毎晩、松岡茉優と寝るためだけに戻ってくる山崎賢人がベッドに潜り込んだあと、直接的な表現をまったく描かなかったことです。村上春樹のデビュー作で、こんな台詞があります。「人が死んだり、人がセックスをする映画は嫌いだ。人は放っておいてもいつか死ぬし、誰かと寝る。」だいたいこんな感じです。そうなんです。当たり前のものは見せず、麗しき過去を曇らせる描写はしない。その点において、作品自体と主人公の男のプライドの高さがシンクロし呼応し、同一の存在だったことがわかります。
この手垢のついた物語で、創作者の悲劇的な性や、共依存の悲しさや、何かができると盲進する儚い姿や、そんなものをちらつかせながら、実際、描いていたのは、彼らへの甘い甘い許しという点で、なかなか独創的かもしれないと思ったのです。どんな過去も、それを美しく飾り立てることは、思っているより難しいことではないのかもしれません。
全てを綺麗な思い出で片付けようとする着地に、ぼくは、なんだかなあと思いつつ、印象にだけは確かに残ったことを否定できないのでした。
辛くて、辛くて、堪えられなかったけれど、ほんとに行きたかったのは、そこなんだよ。松岡茉優の悲しげなまなざしは、劇場を出て、小田急の地下ホームに辿りつくまでに、ずんずん沈み込み、もう浮かび上がれないと思ったに違いありません。電車が入ってくる音にも気づかず、人の流れのままに、電車に乗り込み。真っ暗な窓の外を見つめます。ゆっくりと動き出す電車は、暗いトンネルをどこまでも進んでいきます。ぎゅっと目をつぶり、過呼吸になりそうな瞬間、ガタンという電車の音に反応にして目をあけると、もうそこに闇はありませんでした。代々木上原のホームはとても明るいのです。
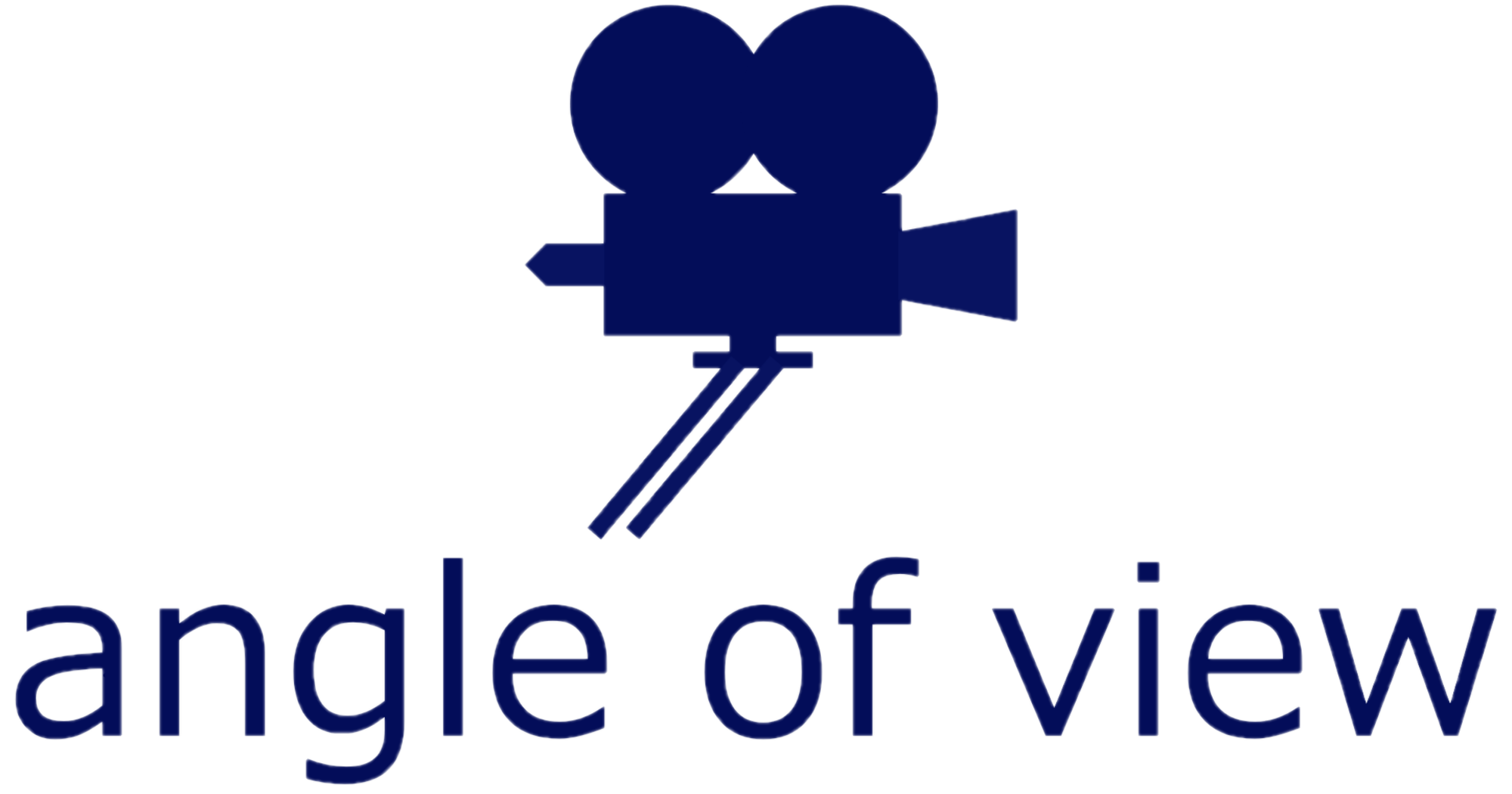








コメント